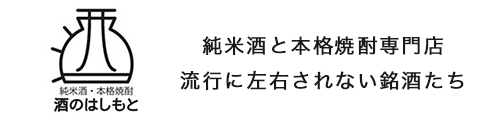米焼酎は飲み方によって表情を大きく変えるのが特徴です。
飲み方のチョイスによって米焼酎を初めて飲む人でも美味しくのめることでしょう。
とはいえ、飲み方を知らなければ、本当の米焼酎の美味しさに触れることなく避けてしまうケースも否めません。
それぞれの飲み方のコツを知っておくだけで、米焼酎をさらに美味しく飲めるので、米焼酎好きな方も、ぜひ参考にしてみてください。
米焼酎の飲み方
焼酎の飲み方は実に様々あり、米焼酎も飲み方が美味しく飲むためのポイントとなります。
蒸留方法や貯蔵期間等様々な違いがあります。
それぞれが美味しくなる飲み方を探ってみましょう。
ただ単に、水やお湯で割るだけではなく、割り方を工夫をすることが大切です。
焼酎単体で飲むのではなく、肴とともに食中でじっくりと楽しむと美味しさの幅がひろがります。
米焼酎を飲む上でおすすめの飲み方をご紹介します。
お湯割り
米焼酎におけるお湯割りは、定番中の定番と言っても過言ではない飲み方です。
米本来の味わいや旨みをじっくり感じることができるので、銘柄ごとが持つ独特の風味を堪能することができます。
お湯割りといっても、単純にお湯で割るだけではありません。
米焼酎のお湯割りは、グラスを2個用意し、熱いお湯を注ぐことから始まります。他方のグラスにお湯を2~3回程度入れ替えお湯の温度を下げてゆきましょう。お茶を入れる要領です。
その後、ゆっくりグラスに這うように米焼酎を注ぎ最後に少々どぼっと注ぎます。
この手法はまさにお湯割り黄金手法 全てのお湯割りに通じます。 2回以上お湯を入れ替えること、決して混ぜないこと、ゆっくり注ぐことがポイントです。
すると、対流が起きて焼酎とお湯が自然に混ざってゆき整ったら飲みましょう。
焼酎を先に入れてしまうと、この対流が起きないため綺麗に混ざらないので要注意です。
ポイントとなるのが米焼酎とお湯の割合でしょう。
この方法であれば米焼酎を2~3割入れて残りの7~8割をお湯で割るという方法です。
米焼酎が持つ米の香りが豊かに引き立ちます。
この手法はまさに全てのお湯割りに通じる黄金手法です!
熱いお湯に焼酎を直接注ぐと味わいや香り崩れていわゆる焼酎が火傷してしまうのでお気をつけ下さい。
そのまま熱いお湯に注ぐよりもマイルドで柔らかな味わいと甘さが引き立ち、香りもたちます。
お湯割りは料理の脂をしっかりと流してくれるので肴と共に飲むと美味しさが広がります。
また身体も温め、冷たい焼酎と比較すると酔い心地も優しくほっこり柔らかいもので楽に楽しめるのです。
お勧めは武者返し、園の露です。
ストレート
お湯や水で割ることなく、米焼酎の風味を直球で楽しみたいなら、ストレートでも。初留など高濃度の特殊なタイプがおすすめです。
お猪口かショットグラスのような小さめの器に、ゆっくりと注ぐと、米焼酎の香りを飛ばすことなく楽しめます。
また、特に高い度数タイプは冷凍庫でキンキンに冷やす飲み方がお勧めです。
0~マイナス5度まで冷やしておくと、とろりとした口当たりになるのが特徴で、何よりアルコール度数の高い米焼酎なので、ストレートでは一度にたくさんの量を飲むことができません。
もちろんここでも肴をつまみながらゆっくりチビチビと飲むのがポイントです。
また、チェイサーを用意することも忘れないようにしましょう。
お勧めは杜氏絹子です。
水割り
お湯割りやストレートと同じく、水割りで米焼酎を飲む人も多く見られます。
減圧蒸留を使って作られたライトなタイプの米焼酎には水割りがおすすめですが常圧蒸留でも美味しい水割りもあります。
お湯割りとの違いは、焼酎を先にグラスに入れる点です。
その理由は、比重にあります。
水より比重が軽いアルコールを先に入れることで、対流が起きやすくなるため、美味しく飲むためには米焼酎を先に入れるように心がけましょう。
作り方はとてもシンプルで、まずはしっかりと冷やしたグラスに、焼酎を注ぎます。
このとき、焼酎の量をコップの1、2割くらいまでにしておくのがポイントです。
焼酎を注いだら、水をコップ7分目位までゆっくりとゆっくりと注ぎ、氷もゆっくりとを入れてゆきます。
こちらも急激な温度変化はストレスを与え、冷えた場合は感じにくいものですがお湯割り同様、香りが尖りやすいのです。
氷を先に入れるならば、出来るだけ氷に当たらない様に焼酎を注いでゆきましょう。
水割りにするときには、軟水のミネラルウォーターを使うことをおすすめします。
多くの蔵元では、仕込みに軟水を使用しており、水割りにしてもよく馴染みます。
硬水にすると、ミネラルが豊富すぎるため、味わいが固くなり米焼酎が持つ風味が崩れてしまいます。
また、氷は出来るだけ自宅で製氷したものを使わず、せっかくなので市販されているロックアイスを選ぶようにしましょう。
余分な成分が入っておらず、溶けにくいので水割りを邪魔することがありません。
お勧めは武者返し、園の露です。
ロック
米焼酎の飲み方として、ロックも外せません。
ストレートで楽しめる素材の味に加えて、時間の経過とともに水割りで感じる飲みやすさまで楽しめるのはロックの醍醐味といえるでしょう。
米焼酎をロックで楽しむ上で欠かせないのは、グラスを冷やしておくことです。
そして、大きめの氷をたっぷりと入れ、ゆっくりと注ぎ入れます。
小さな氷ではすぐに溶けてしまうので、ロックには相応しくありません。
焼酎を注ぐ前に、一度マドラーで混ぜて余分な水を捨てるのもポイントです。
この動作によって、注がれた米焼酎が氷にしっかりと馴染んでくれま
水割り同様、こちらもロックアイスがお勧めです。
また器にも重点を置きたいところでロックグラスを使うのがおすすめです。
ロックグラスとは、「オールド・ファッション・グラス」とも呼ばれ、背が低く口が広いといった特徴があります。
重さや大きさ、ガラスの厚さなどはそれぞれのコップによって個性があるので、自分の手に馴染むグラスを選ぶようにするとよいでしょう。
お勧めは蔵の隠き魅やげです。
ソーダ割り
近年人気が高まっている米焼酎の飲み方がソーダ割りです。
作り方は、ハイボールとほとんど同じなので馴染みがある人も多いでしょう。
まず、グラスにたっぷりと氷を入れてかき混ぜます。
こうすることで、グラスが良く冷えて米焼酎のソーダ割りがより美味しくなります。
混ぜた際に溶けた氷の水は捨ててから、ゆっくり氷に当たらない様に焼酎を注ぎ、次に良く冷えた炭酸水を注ぎましょう。
最後に氷をマドラー等で氷を持ち上げて焼酎と炭酸を馴染ませ出来上がりです。
ソーダ割りは、ビールを飲むような感覚で米焼酎を飲みたい人におすすめです。
そのため、アルコール度数を低めするように割るのがポイントとなります。
割方はお好みですが例えば、25度程度の米焼酎の場合、1:3または4で炭酸水を多く入れる割合も目安です。
また、ソーダ割りに使う炭酸水は、軟水が使われたものにすると米焼酎に良く馴染みます。
熱燗
日本酒と同じように、米焼酎を熱燗にするのも一つの飲み方です。
お湯割りは、お湯を注いだ湯飲みに米焼酎を加えて飲みますが、熱燗は焼酎を入れた酒器をそのまま温めます。
熱燗にすることで、米の香りがさらに引き立つので、ツウ好みの飲み方といえるでしょう。
熱燗の作り方としてポピュラーなのは、湯煎です。
日本酒を温めるように、焼酎を徳利に注ぎ、沸騰して火を止めた直後のお湯に徳利ごと入れます。
2分~3分程度温め膨張してきたら徳利を取り出して完成です。
熱いとシャープに、ぬるいと甘みが強調されてそれぞれの味わいがあります。
米焼酎が生まれた球磨地方の球磨焼酎では、「ガラ」と呼ばれる酒器を使って熱燗を作るのがおすすめです。
直火にかけられる酒器であり、一般的に「チョク」という杯とセットで使われます。
普段は水割りやお湯割りを楽しんでいる人も、熱燗にすることで米焼酎の新しい魅力を知ることができるでしょう。
燗ロック(球磨焼酎の「武者返し」常圧蒸留がおすすめ)
上記にもある「ガラ(黒じょか)」、無い場合は徳利でもちろりでも構いません。
米焼酎を注ぎできれば直火又は湯煎で(せめて湯煎)温めます。
湯気が出始める頃がだいたい40℃くらい。
揺らして温度を馴染ませ、日本酒でいう熱燗くらい(55度~60℃またはそれ以上)までしっかりと温めます。
そして、グラスに市販のロックアイスを入れます。
氷に当たらないように、縁から注ぎ、そっとステアします。
この飲み方を「燗ロック」といい、非常に米焼酎の特徴が出やすくうま味たっぷりの美味しい焼酎に変身します。
また、普通にロックを作り、そこに熱いお湯をスプーン1杯程入れてステア。
これもお米の香り高い甘いロックに仕上がる美味しい飲み方です。
前割り
飲み方として、もう一つ挙げておきたいのが前割りです。
5対5で水割りを事前に作り、1日~数日の間冷蔵庫で寝かせて飲む方法で、米焼酎と水をしっかりと馴染ませることができます。お燗で温めても冷やしてもも美味しく驚くほどに味わいが馴染み驚くほどほどまろやかな味わいにかわります。前割の場合は5対5で作るとしっかりと馴染みます。
冷やして冷酎として飲むか、ふくよかなお燗で温めるか。
どちらもスイスイと杯が進んでゆきます。
最近は、前割りに適した焼酎サーバーも出ており、遮光タイプになっているものもあるため、劣化を防ぐことも可能です。
もちろんペットボトルや瓶でも構いません。
また長期に渡り保管する場合、味わいがダレてきたらスプーン1杯ほどの焼酎を足して下さい。
少々若さも出てきますが再度、馴染んでゆきます。
米焼酎の魅力は飲み方によって七変化
いかがでしたでしょうか。
この記事をお読みいただくことで、米焼酎の飲み方がおわかりいただけたと思います。
米焼酎の魅力は、飲み方によって様々であり、自分好みの飲み方を探しやすい点もポイントです。
銘柄や気分に合わせて、飲み方を変えながら楽しむのもよいでしょう。
酒のはしもとでは、目利きした焼酎や純米酒を多数販売しております。
詳しくはこちらをご覧ください。